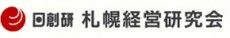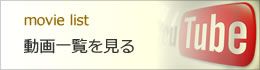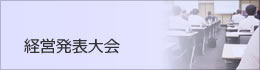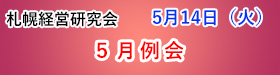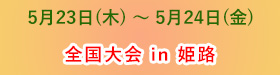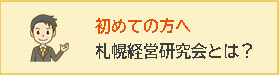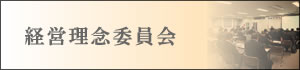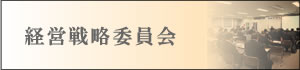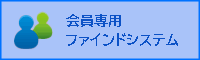【5月例会】今こそ攻め時!市場を勝ち抜くクロッシング戦略とは?
- 2025-05-12 (月) 15:41
- イベント
5月28日 (水) 18:30から、豊水会館にて5月例会が開催されます。
【例会テーマ】
今こそ攻め時!市場を勝ち抜くクロッシング戦略とは?
「自社の経営方針に、心から『腹落ち』できているだろうか?」
「作った経営戦略が、本当に自社に合っていて、市場で勝てるものになっているだろうか?」
こんな問いを、一度はご自身に投げかけたことがあるのではないでしょうか。
机上で練った方針書が、どうも自分自身にしっくりこない。社員に話しても、どこか響いていないように感じる。
そんな悩みを抱えている経営者の方に、ぜひ知っていただきたい学びのイベントです。
この例会のテーマは、まさに多くの経営者が知りたいであろう「今こそ攻めどき 市場勝ち クロッシング戦略とは」という、非常に実践的な内容です。
経営方針は、単に「会社の方針を伝える」というだけでなく、「共感を得ることにより経営資源を得ること」 です。
経営資源とは、人・物・金・情報。
社員からの協力、顧客満足、金融機関からの資金、そして方針策定・実行に必要な情報。
これらを得るためには、関わる人々の共感が不可欠なのです。
そして、数ある経営資源の中で、最も獲得するのが簡単で、かつ最も重要な経営資源は「経営者自分自身」であるという点です。
なぜなら、自分自身を動かせるのは自分だけだから。最も身近で、最も影響力が大きい経営資源は、あなた自身なのです。
だからこそ、経営方針発表は、まず経営者自身が方針に「腹落ち」し、心から納得し、情熱を燃やせる状態になるためのプロセスとして、非常に重要な意味を持つのです。
自分自身が共感できない方針で、どうして他の誰かの共感を得られるでしょうか。
では、どうすれば経営者自身が、自社の経営方針に深く「腹落ち」し、自分自身という経営資源を強化できるのでしょうか?
経営方針の策定・発表のプロセスの中に、経営者自身が「気づき」を得て、自分という経営資源を獲得できる3つの重要な場面があります。
経営方針書には、会社概要、理念、沿革、強み・弱み、外部環境分析、戦略、計画、財務など、様々な要素が盛り込まれています。
方針書のフォーマットに沿って、全体として一貫性(インテグリティ)を保つように策定を進める中で、自社や経営環境について「分からないこと」や「これで良いのか?」という疑問が必ず湧いてきます。
社員や顧客との対話を通じて情報を集め、理念から再度見直す。このサイクルを回すこと自体が、経営者自身に多くの「気づき」をもたらし、方針への理解を深めるのです。
作った方針を、自分の言葉で声に出して語ってみましょう。
例えば、研究会や勉強会の場で発表してみることは、最高の機会です。
実際に話してみると、スラスラと話せる部分と、言葉に詰まったり、どこか引っかかりを感じる部分があることに気づくはずです。
これは、あなたが方針に対して「共感できている部分」と「まだ腹落ちできていない部分」の明確なサインなのです。
言葉だけでなく、発表時の態度や表情にもそれは表れます。発表は、まさに自分自身を客観的に見つめ直す鏡となります。
発表を聞いた他者からのフィードバックは、自分一人では気づけなかった「盲点」を教えてくれます。
様々な意見やアドバイスをもらう中で、最初は反論したくなることもあるかもしれません。
しかし、それらの声と自分の考えを照らし合わせるうちに、「何が最も重要なのか」「今、自分がまず変えるべきことは何なのか」といった優先順位が見えてきます。
このフィードバックこそが、方針をさらに磨き上げ、そして経営者自身を成長させるための大きな「気づき」となるのです。
これらのプロセスを経て、経営者自身が方針に心から「腹落ち」し、「自分という経営資源」をより強固なものにすることができるのです。
5月例会のテーマである「今こそ攻めどき 市場勝ち クロッシング戦略とは」 は、この「腹落ち」した経営方針の中核をなす、非常に重要な要素です。
この例会で深掘りされた「クロッシング」とは、まさに自社の強み、弱み、機会、脅威(SWOT分析の4要素)を掛け合わせたクロス分析 のことです。
具体的には、可能性のある市場やニーズといった「機会」に、自社の持つ物理的な経営資源やノウハウ、経験などの「強み」を掛け合わせることによって、自社独自の、積極的に「攻める」「投資する」戦略をあぶり出す作業です。
闇雲に市場に挑むのではなく、自社の足元(強み)と市場の可能性(機会)をしっかりと掛け合わせるからこそ、勝てる戦略が見えてくる。
そして、この戦略策定の質が、経営方針全体の実効性を左右する鍵となるわけです。
さらに、経営方針書をより深く理解し、そして何より関係者の「共感」を得るための仕組みとして、「ゴールデンサークル」があります。
これはサイモン・シネック氏が提唱した概念で、物事を「なぜ (Why) → どうやって (How) → 何を (What)」の順で伝えることで、人々の共感を得やすくなるというものです。
一般的な説明は「何をやるか (What)」「どうやってやるか (How)」から始めがちですが、真に人々の心を動かし、共感を生むのは、そのなぜ (Why)」の部分、すなわち信念や理念です。
経営方針書も同様です。
単に「何をやるか」「どうやってやるか」だけを羅列するのではなく、「なぜそれをやるのか(Why)」、つまり自社の理念や目的に基づいて語り始めることで、社員をはじめとする関係者の共感を得やすくなります。
この「共感を得る仕組み」こそがゴールデンサークルそのものであり、方針発表の目的に深く結びついているのです。
経営方針書は、単なる形式的な書類ではありません。
それは、経営者自身が自社への「気づき」を得て、「自分」という最も重要な経営資源を強化し、関係者の共感を通じて事業を推進するための強力な羅針盤となり得ます。
そして、5月例会でテーマとなっている「クロッシング戦略」は、その羅針盤が指し示す方向が、市場で勝ち抜くための具体的な道筋となっているかを見極める核心です。
自社の「強み」と市場の「機会」を掛け合わせることで、貴社だけの「攻める」戦略が見えてきます。
そして、策定した方針で人々の共感を得るためには、「ゴールデンサークル」の考え方が非常に有効です。
5月例会では、このように経営の根幹に関わるテーマについて、基礎的な考え方を学び、当日は具体的な手法や実践事例を、実際に事業を経営されているお二人(株式会社北海道バイオインダストリー代表 村上季隆さん、アンカードシステムズ株式会社代表 大坂敏郎さん)から直接学ぶ機会です。
現場の最前線で活躍されている経営者の生の声ほど、説得力があり、実践につながるものはありません。
「腹落ち」する経営方針を手にし、市場で勝つための「クロッシング戦略」を学び、そして自分自身という経営資源を最大限に活かすためのヒント。これらは、経営者として、事業の成長をさらに加速させるために不可欠な要素です。
ぜひ、日々の経営の傍ら、このような学びの場に積極的に参加し、同じ志を持つ経営者仲間と共に学びを深めてみませんか?
きっと、貴社の未来を切り拓く具体的な一歩が見つかるはずです。
【講演者】
村上季隆さん(株式会社北海道バイオインダストリー)
大坂敏郎さん(アンカードシステムズ株式会社)
【プログラム詳細】
日時:2025年5月28日(水) 18:30〜20:30
会場:豊水会館
参加費:会員・社員さん 無料、一般の方 2,000円
懇談会店:グランド居酒屋富士
懇談会参加費:4,500円
このイベントは経営研究会の会員のみならず、社員さんや一般の方も参加可能です。
一般の方は、こちらからお申込み下さい。
お申込みはこちらから

最後までお読みいただき、ありがとうございます。
「いいね!」や「+1」などのボタンを押して応援いただけたら嬉しいです(^^♪
下のコメント欄に、感じた事や気づいたことなども書き込んで下さいね!
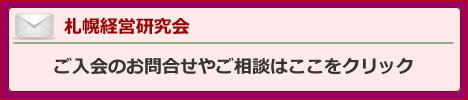
【例会テーマ】
今こそ攻め時!市場を勝ち抜くクロッシング戦略とは?
「自社の経営方針に、心から『腹落ち』できているだろうか?」
「作った経営戦略が、本当に自社に合っていて、市場で勝てるものになっているだろうか?」
こんな問いを、一度はご自身に投げかけたことがあるのではないでしょうか。
机上で練った方針書が、どうも自分自身にしっくりこない。社員に話しても、どこか響いていないように感じる。
そんな悩みを抱えている経営者の方に、ぜひ知っていただきたい学びのイベントです。
この例会のテーマは、まさに多くの経営者が知りたいであろう「今こそ攻めどき 市場勝ち クロッシング戦略とは」という、非常に実践的な内容です。
経営方針発表の「本当」の目的とは?
経営方針は、単に「会社の方針を伝える」というだけでなく、「共感を得ることにより経営資源を得ること」 です。
経営資源とは、人・物・金・情報。
社員からの協力、顧客満足、金融機関からの資金、そして方針策定・実行に必要な情報。
これらを得るためには、関わる人々の共感が不可欠なのです。
そして、数ある経営資源の中で、最も獲得するのが簡単で、かつ最も重要な経営資源は「経営者自分自身」であるという点です。
なぜなら、自分自身を動かせるのは自分だけだから。最も身近で、最も影響力が大きい経営資源は、あなた自身なのです。
だからこそ、経営方針発表は、まず経営者自身が方針に「腹落ち」し、心から納得し、情熱を燃やせる状態になるためのプロセスとして、非常に重要な意味を持つのです。
自分自身が共感できない方針で、どうして他の誰かの共感を得られるでしょうか。
経営者自身が「腹落ち」するための3つの「気づき」の機会
では、どうすれば経営者自身が、自社の経営方針に深く「腹落ち」し、自分自身という経営資源を強化できるのでしょうか?
経営方針の策定・発表のプロセスの中に、経営者自身が「気づき」を得て、自分という経営資源を獲得できる3つの重要な場面があります。
1. 方針を「策定する過程」での気づき
経営方針書には、会社概要、理念、沿革、強み・弱み、外部環境分析、戦略、計画、財務など、様々な要素が盛り込まれています。
方針書のフォーマットに沿って、全体として一貫性(インテグリティ)を保つように策定を進める中で、自社や経営環境について「分からないこと」や「これで良いのか?」という疑問が必ず湧いてきます。
社員や顧客との対話を通じて情報を集め、理念から再度見直す。このサイクルを回すこと自体が、経営者自身に多くの「気づき」をもたらし、方針への理解を深めるのです。
2. 方針を「発表する」ことでの気づき
作った方針を、自分の言葉で声に出して語ってみましょう。
例えば、研究会や勉強会の場で発表してみることは、最高の機会です。
実際に話してみると、スラスラと話せる部分と、言葉に詰まったり、どこか引っかかりを感じる部分があることに気づくはずです。
これは、あなたが方針に対して「共感できている部分」と「まだ腹落ちできていない部分」の明確なサインなのです。
言葉だけでなく、発表時の態度や表情にもそれは表れます。発表は、まさに自分自身を客観的に見つめ直す鏡となります。
3. 発表後の「フィードバック」による気づき
発表を聞いた他者からのフィードバックは、自分一人では気づけなかった「盲点」を教えてくれます。
様々な意見やアドバイスをもらう中で、最初は反論したくなることもあるかもしれません。
しかし、それらの声と自分の考えを照らし合わせるうちに、「何が最も重要なのか」「今、自分がまず変えるべきことは何なのか」といった優先順位が見えてきます。
このフィードバックこそが、方針をさらに磨き上げ、そして経営者自身を成長させるための大きな「気づき」となるのです。
これらのプロセスを経て、経営者自身が方針に心から「腹落ち」し、「自分という経営資源」をより強固なものにすることができるのです。
市場で勝つ!例会テーマ「クロッシング戦略」の核心
5月例会のテーマである「今こそ攻めどき 市場勝ち クロッシング戦略とは」 は、この「腹落ち」した経営方針の中核をなす、非常に重要な要素です。
この例会で深掘りされた「クロッシング」とは、まさに自社の強み、弱み、機会、脅威(SWOT分析の4要素)を掛け合わせたクロス分析 のことです。
具体的には、可能性のある市場やニーズといった「機会」に、自社の持つ物理的な経営資源やノウハウ、経験などの「強み」を掛け合わせることによって、自社独自の、積極的に「攻める」「投資する」戦略をあぶり出す作業です。
闇雲に市場に挑むのではなく、自社の足元(強み)と市場の可能性(機会)をしっかりと掛け合わせるからこそ、勝てる戦略が見えてくる。
そして、この戦略策定の質が、経営方針全体の実効性を左右する鍵となるわけです。
共感を生む「ゴールデンサークル」という羅針盤
さらに、経営方針書をより深く理解し、そして何より関係者の「共感」を得るための仕組みとして、「ゴールデンサークル」があります。
これはサイモン・シネック氏が提唱した概念で、物事を「なぜ (Why) → どうやって (How) → 何を (What)」の順で伝えることで、人々の共感を得やすくなるというものです。
一般的な説明は「何をやるか (What)」「どうやってやるか (How)」から始めがちですが、真に人々の心を動かし、共感を生むのは、そのなぜ (Why)」の部分、すなわち信念や理念です。
経営方針書も同様です。
単に「何をやるか」「どうやってやるか」だけを羅列するのではなく、「なぜそれをやるのか(Why)」、つまり自社の理念や目的に基づいて語り始めることで、社員をはじめとする関係者の共感を得やすくなります。
この「共感を得る仕組み」こそがゴールデンサークルそのものであり、方針発表の目的に深く結びついているのです。
経営方針書は、単なる形式的な書類ではありません。
それは、経営者自身が自社への「気づき」を得て、「自分」という最も重要な経営資源を強化し、関係者の共感を通じて事業を推進するための強力な羅針盤となり得ます。
そして、5月例会でテーマとなっている「クロッシング戦略」は、その羅針盤が指し示す方向が、市場で勝ち抜くための具体的な道筋となっているかを見極める核心です。
自社の「強み」と市場の「機会」を掛け合わせることで、貴社だけの「攻める」戦略が見えてきます。
そして、策定した方針で人々の共感を得るためには、「ゴールデンサークル」の考え方が非常に有効です。
5月例会では、このように経営の根幹に関わるテーマについて、基礎的な考え方を学び、当日は具体的な手法や実践事例を、実際に事業を経営されているお二人(株式会社北海道バイオインダストリー代表 村上季隆さん、アンカードシステムズ株式会社代表 大坂敏郎さん)から直接学ぶ機会です。
現場の最前線で活躍されている経営者の生の声ほど、説得力があり、実践につながるものはありません。
「腹落ち」する経営方針を手にし、市場で勝つための「クロッシング戦略」を学び、そして自分自身という経営資源を最大限に活かすためのヒント。これらは、経営者として、事業の成長をさらに加速させるために不可欠な要素です。
ぜひ、日々の経営の傍ら、このような学びの場に積極的に参加し、同じ志を持つ経営者仲間と共に学びを深めてみませんか?
きっと、貴社の未来を切り拓く具体的な一歩が見つかるはずです。
【講演者】
村上季隆さん(株式会社北海道バイオインダストリー)
大坂敏郎さん(アンカードシステムズ株式会社)
【プログラム詳細】
日時:2025年5月28日(水) 18:30〜20:30
会場:豊水会館
参加費:会員・社員さん 無料、一般の方 2,000円
懇談会店:グランド居酒屋富士
懇談会参加費:4,500円
このイベントは経営研究会の会員のみならず、社員さんや一般の方も参加可能です。
一般の方は、こちらからお申込み下さい。
お申込みはこちらから

最後までお読みいただき、ありがとうございます。
「いいね!」や「+1」などのボタンを押して応援いただけたら嬉しいです(^^♪
下のコメント欄に、感じた事や気づいたことなども書き込んで下さいね!
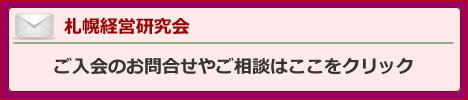
関連したこちらの記事もご覧下さい
-

2026.02.01
【2/17開催】第1回通常総会と2月例会のお知らせ
-

2026.01.06
2026年新年交流例会のご案内
-

2025.10.24
【11月例会】TTで気づく 自社の新たな可能性!
-

2025.09.10
【10月例会】本部主催勉強会 理念から生まれるビジネスモデル
-

2025.09.02
【9月例会】経営者の原体験が理念とビジョンを創る